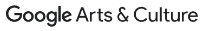韓国やきもの史
韓国のやきものの歴史も、やはり土器にはじまります。紀元前5000年頃の新石器時代に紐のような装飾を表面に貼りつけた突帯文(とったいもん)土器があらわれ、やがて斜線文をきざんだ櫛目文(くしめもん)土器が全土に広がります。紀元前1000年頃には、弥生土器のように何も文様をつけない無文(むもん)土器へと変り、紀元前後には中国からロクロと窯の技術がつたわり、瓦のような瓦質(がしつ)土器が登場します。この瓦質土器をもとに三国時代の高句麗(こうくり)・新羅(しらぎ)・百済(くだら)・加耶(かや)では、陶質(とうしつ)土器とよばれる灰黒色の土器がつくられました。さらにこの頃、釉薬をかけて低い温度で焼く緑釉(りょくゆう)陶器が登場し、つづく統一新羅時代に大きく発展をとげます。
高麗(こうらい)時代〔918~1392年〕になると、10世紀頃に、韓国ではじめて青磁と白磁が焼かれました。この青磁は中国の浙江(せっこう)省北部に広がる五代越窯(えつよう)の影響によって生まれましたが、12世紀には、「翡色(ひしょく)」と呼ばれる深い青みを帯びる美しい釉色、白や黒に発色する土をはめこんで装飾する象嵌(ぞうがん)という技法など、高麗青磁特有の姿となっていきます。こうした高麗青磁の二大生産地として有名なのが、南西部に位置する康津(カンジン)と扶安(ブアン)です。また、鉄の顔料で文様を描く青磁鉄絵や、黒釉等が焼かれました。このように頂点をきわめた青磁も、14世紀頃からの政治不安のなかで、実用的で大量生産にふさわしい、灰色を帯びて堅く焼きしまった姿へと変っていきます。
つづいて朝鮮時代〔1392~1910〕になると、高麗王朝末期の高麗青磁に白土でさまざまな装飾をほどこした粉青(ふんせい) 〔日本では「三島」とも呼ぶ〕が、新たに登場しました。そこには、高麗青磁の細やかな文様とは異なり、自由で大胆な装飾世界を見ることができます。例えば、粗い刷毛の跡が文様のように残る刷毛目や、白泥の中に浸しがけする粉引、とくに、忠清南道公州郡反浦面鶏龍山の周辺で焼かれたことから「鶏龍山」とも呼ばれた粉青鉄絵は有名です。こうした粉青の一部は、日本では「高麗茶碗」としても伝わっています。
いっぽうで、白磁が15世紀初期頃には本格的に作られ、朝鮮王朝の統治理念であった儒教思想にふさわしい清潔で簡素なものとして、主役の座をしめるようになります。白磁は王の器とされ、京畿道広州一帯にひろがる官窯(かんよう)で焼かれましたが、地方でも16世紀後半頃には焼かれるようになります。いっぽう、白磁にコバルト顔料で描く青花(せいか)〔染付〕は15世紀半ばには生産され、芸術的で清新な朝鮮王朝特有のものとして展開しますが、17世紀には、コバルト顔料の中国からの輸入が一時的に困難となり、それにかわって、褐色に発色する鉄絵具で文様を描く鉄砂(てっしゃ)が流行します。18世紀前半には、日本で「秋草手(あきくさで)」と呼ばれる、乳白色の白磁に淡い色で文様を描く青花が登場します。1752年に広州分院里に官窯が固定されると、安定した環境のもとで、青花はもちろん、鉄砂や、赤色に発色する辰砂(しんしゃ)などを巧みに用いた作品のほか、文人の好みに合せた文房具や酒器などもつくられました。19世紀になると、中間階層の成長により、長寿や子宝を願う吉祥文や民画的な要素を含んだ現世利益的な文様が新たにあらわれ、それはまた工芸の代表的な表現様式の一つともなりました。